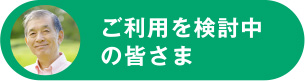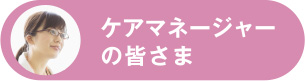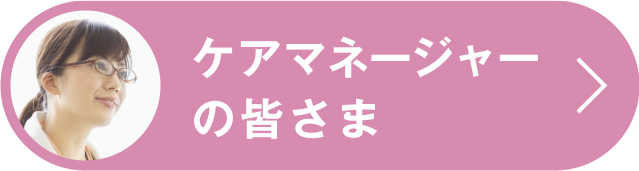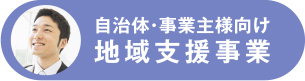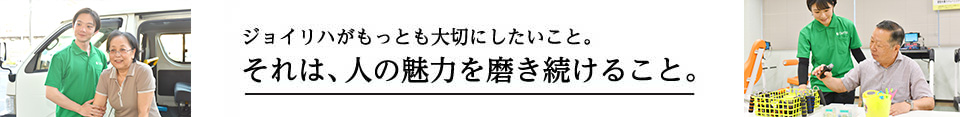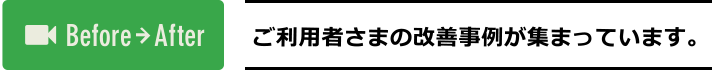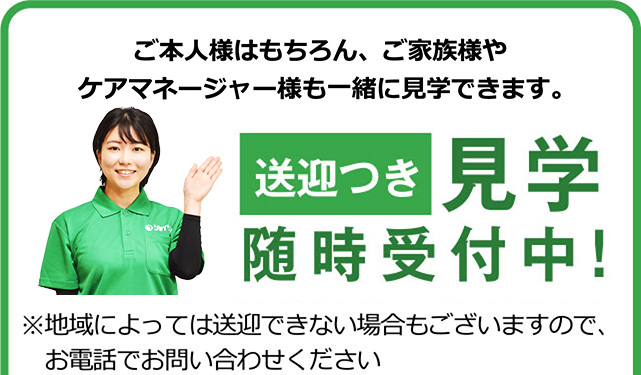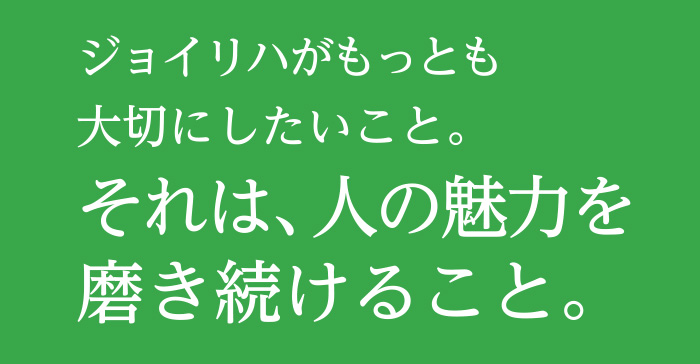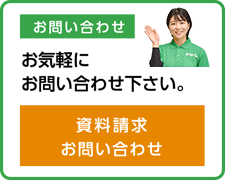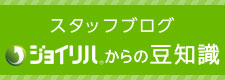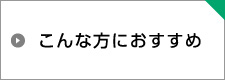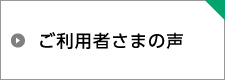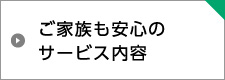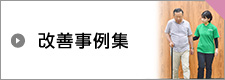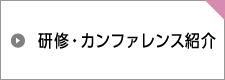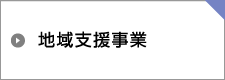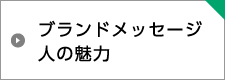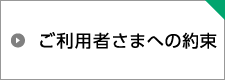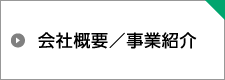デイサービス(通所介護) ジョイリハ
デイサービス(通所介護)ジョイリハは、平成16年の開業以来、介護予防に特化した、1日3時間のリハビリ施設の運営を行っております。
ジョイリハは、介護予防事業のパイオニアであるノウハウを最大限に生かし、ますます地域における「元気」のハブとしてご利用者さまの暮らしに貢献してまいります。
ご利用者さまの改善事例が集まっています。
ジョイリハ 3つの特長
1科学的根拠に基づいた、独自のプログラムを導入
90日で杖歩行者の80%以上が
歩行機能・バランス機能の改善を達成!!

約3000名のジョイリハご利用者さまのうち、比較検討可能な方267名のデータ推移を抽出し、杖歩行者30名の方を観察しました。90日間のプログラム実施前後で比較したところ、「バランス能力」「直線的移動能力」「総合的移動能力」などについて、82〜92%の方に機能向上が見られました。ジョイリハが提供する機能訓練は、科学的な有効性が立証されています。
ジョイリハが提供する機能訓練は、科学的な有効性が立証されています。
21日3時間、一人ひとりに個別のメニューをご提案
理学療法士、作業療法士、看護師など
専門家が複合的にプログラムを立案

抱えている課題、体調などによってご利用者さまの目標は変わります。1日3時間を有効に使っていただくため、グループレッスン、個別メニューなどを組み合わせて、その方に最適なプログラムを作成。また、ご自宅でできる体操「家トレ」などもご紹介し、日常的に運動の週間を身につけながら、ご自分のペースで機能改善を目指していただきます。
グループレッスン、個別メニューなどを組み合わせて、その方に最適なプログラムを作成いたします。
 運動機能向上
運動機能向上グループレッスンや歩行練習、マシントレーニングなど個別の運動メニューを行います。
 認知症予防
認知症予防指体操や簡単な脳トレを運動と一緒に行うことで認知症の予防に役立ちます。
 口腔機能向上・低栄養予防
口腔機能向上・低栄養予防口腔機能の向上は誤嚥予防や豊かな表情づくり、楽しくおしゃべりに役立ちます。
3介護予防専門の、オリジナルマシンを使用
ジョイリハが開発した
オリジナルのマシンで
高齢者や女性でも安心、安全


マシンごとにモニターを完備し、ご利用者様ごとのQRコードを読み込むことで、AIによって負荷自動設定や運動履歴をマシンのシステムへ取り込む事が出来ます。ご利用者様一人ひとりに合わせた最適な運動量となるため、安心してご利用いただけます。
 QRコードリーダー
QRコードリーダー マシンとの連動
マシンとの連動 オリジナルマシン
オリジナルマシン
新着情報
ご利用者さまのお喜びの声
 74歳・男性 要介護2
74歳・男性 要介護2ジョイリハに通ってから、姿勢を正し胸を張って歩けるようになりました。
 85歳・女性 要介護1
85歳・女性 要介護1杖をつきながら一人で歩けるようになりました。あきらめずに運動を続けてよかったです。
 79歳・男性 要介護1
79歳・男性 要介護1明るいスタッフがそろっていて、気持ちよく通える施設です。
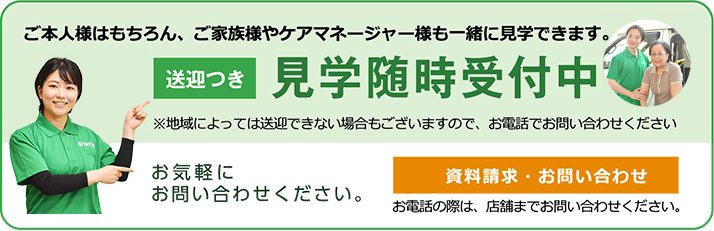

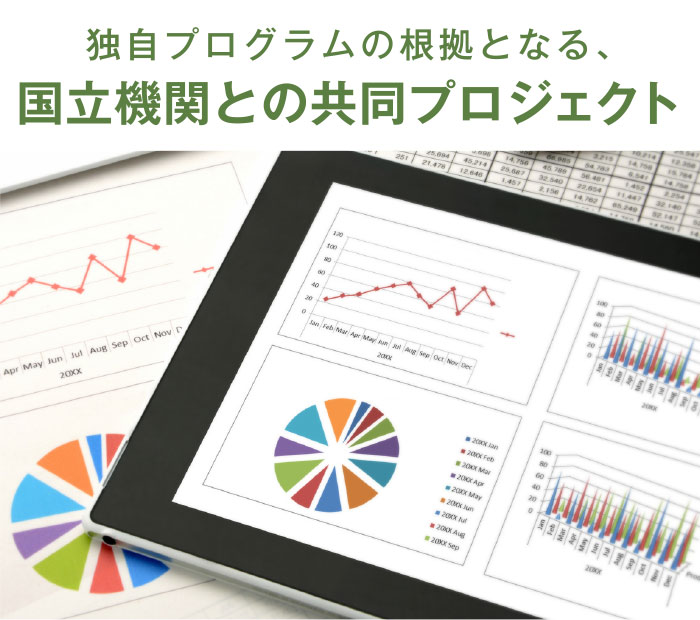



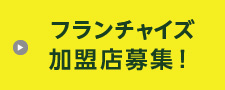
 お近くの店舗検索はこちら>
お近くの店舗検索はこちら>